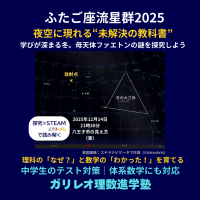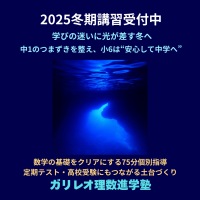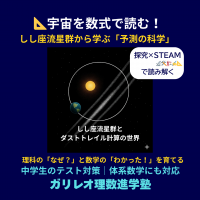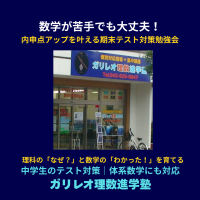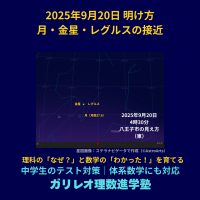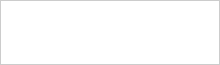前回の記事では、アジサイの花びらのように見える部分が、実は「花弁」ではなく「萼(がく)」であること、そしてその目立つ構造が「装飾花」として虫を引きつける役割を担っていることをご紹介しました。
今回は、その続きを一緒に考えてみましょう。
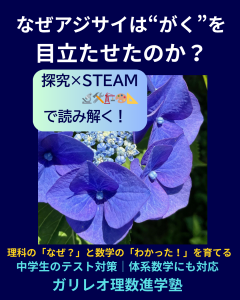
なぜアジサイは“がく”を目立たせたのか?──探究の入口は、ここから。
でも──
なぜ花びらじゃなく、“がく”を目立たせたの?
一見あたりまえに見えるその姿にも、実は自然界の中で生き抜くための、精巧で合理的な“戦略”が隠されているかもしれません。
萼や花弁は、もともと“葉”だった?
まず知っておきたい前提があります。
植物の花のパーツ──花弁や萼──は、もともと“葉”が進化して変化したものだと考えられているのです。
今では形も役割も違いますが、いずれも出発点は同じ。
つまり、花弁も萼も、植物にとっては「葉の使い道のひとつ」だということです。
萼は「つぼみを守る」ためのパーツ?──でも本当にそれだけ?
中学受験や中学校の理科では、「萼にはつぼみを守るはたらきがある」と学びます。
実際、萼は花弁より厚くて丈夫で、風雨から中の花を守る“よろい”のような構造になっています。
でも──
アジサイの萼は、その“守る”ための構造であるはずなのに、なぜかとても目立つように進化しているのです。
「守るためのパーツ」が、なぜ「虫を呼ぶための目印」になったのか?
✨探究の視点:
ここで、考えてみましょう。もしあなたが植物だったら──
「虫に見つけてもらうために、目立つパーツを作りたい!」と思ったとき、どんな手段を選びますか?
なぜ花弁ではなく、萼を目立たせたのか?
植物にとって“見つけてもらうこと”は、子孫を残すために非常に重要です。
とくにアジサイのような虫媒花(ちゅうばいか)は、虫を誘って花粉を運んでもらう必要があります。
多くの植物は花弁を発達させて目立たせますが、アジサイはあえて「花弁」ではなく「萼(萼片)」を発達させる道を選びました。
では、なぜアジサイは「花弁」ではなく「萼」を使ったのでしょうか?
✨探究の視点:
まずは、自分なりの仮説を立ててみましょう。
「なぜこうなっているのだろう?」──そう考えることから、すべての探究は始まります。
🔍考えはまとまりましたか?
では、研究者たちが注目した3つの理由を見てみましょう。
【理由1】萼はもともと丈夫で、壊れにくい
萼はつぼみを守る役目をもつだけあって、厚くてかたく、構造がしっかりしています。
そのため、大きくなっても壊れにくく、虫が触れても問題ありません。
目立たせるには、まず“壊れないこと”が大切──この観点で、萼は理想的な素材だったのです。
【理由2】新しく作るより、“再利用”のほうがエネルギー効率がいい
花弁を目立たせるには、色・形・香り・蜜など、さまざまな要素を整える必要があります。
そのぶん、構造の形成や物質の合成には多くのエネルギーがかかります。
一方、萼はもともとつぼみを守るためのパーツであり、すでにある構造を活かせるという利点があります。
色を加えて少し大きくするだけで目立たせられるなら、新たに花弁を作るよりも、省エネで合理的な進化といえるでしょう。
【理由3】虫にとって重要なのは「花弁かどうか」じゃない
虫は「これは花弁かな?」と考えて寄ってくるわけではありません。
反応するのは、「色」「形」「配置」など、“目立つかどうか”です。
つまり、「目立てばOK」。その役割が果たせるなら、花弁でも萼でも関係ないのです。
「守るパーツ」が主役になる──“再利用の進化”
アジサイでは、「守るための萼」が「虫を呼ぶための看板」へと進化しました。
これは、進化の世界でよく見られる「転用(co-option)」という現象。
ある機能を持った構造が、まったく別の目的に使われるようになることです。
たとえば──
鳥の羽は、もともと爬虫類の「うろこ」が変化したものだと考えられています。
既存の構造を“再利用”して、新たな機能をもたせる。
それは、生き物たちが生き残るために選んできた、とても合理的な工夫なのです。
日常の“あたりまえ”から「なぜ?」を見つける力
「なんで花びらじゃなく、がくなの?」──この素朴な問いこそが、理科的探究の第一歩です。
あなたなら、虫をひきつけるためにどんな工夫をするでしょうか?
葉を大きくする? 匂いを強くする? 色を派手にする?
「もし自分がアジサイだったら?」と想像してみることで、進化の工夫がより深く理解できるようになります。
✨探究の視点:
虫は本当に「目立つもの」だけを見ているのでしょうか?
──もしかすると、「色」より「匂い」が大事なのかもしれません。
それとも、「配置」や「形」のほうが虫にはわかりやすいのでしょうか?
どんな要素に反応しているのか、実際に観察したり、自分で調べたりしてみたくなりませんか?
その「問い」こそが、理科の学びの出発点です。
➡ そしてこうした「なぜ?」から始まる思考は、
定期テストや入試で求められる「理由を説明する力」「考えを言葉で表現する力」に、まっすぐつながっていきます。
🌿まとめ:花びらではなく、“萼”が主役になった進化戦略
アジサイが目立たせたのは、花弁ではなく、「つぼみを守る萼片」でした。
でもそれは、壊れにくく、省エネで、虫を惹きつける──そんな合理的な選択だったのです。
植物の進化には、「使えるものを最大限に活かす」知恵がつまっています。
次にアジサイを見かけたときには、ぜひ思い出してください。
なんで花びらじゃなくて“萼”なんだろう?
その問いが、あなたの理科のチカラを育ててくれます。
🔎STEAMで深めるアジサイの進化戦略
🔬 科学(Science)|植物の進化と遺伝子の働き
植物の花のパーツ(花弁・萼など)は、もともと“葉”が変化したものと考えられています。
この変化には、「花器官アイデンティティ遺伝子」と呼ばれる特定の遺伝子群(例:MADS-box遺伝子)が関与し、葉から花の各器官へと分化させる“遺伝的スイッチ”の役割を果たします。
理科の授業で学ぶ「観察→仮説→説明」のサイクルを活用して、このような進化のしくみにアプローチできます。
🛠 技術(Technology)|見えない違いを「見える化」する力
顕微鏡を使えば、アジサイの萼と本物の花(両性花)の構造や細胞の違いを観察できます。
色素の分布、細胞壁の厚み、表面の模様など──肉眼では見えない差異を“見える化”できる技術の力こそ、現代科学の基盤です。
STEAM教育では、こうした「ツールで世界を広げる力」を育てることが重視されます。
🏗 工学(Engineering)|壊れにくく目立つ「構造の工夫」
アジサイの萼は、花弁に代わって“目立つ看板”としての役割を果たすと同時に、風や雨にも強いという耐久性も兼ね備えています。
このように「見た目の美しさ」と「物理的な強さ」の両立は、構造工学や材料設計にも活かされる発想であり、「バイオミミクリー(生体模倣)」として注目されています。
🎨✍️ 芸術・リベラルアーツ(Arts)|自然が教えるデザインと表現
アジサイの装飾花は、色とりどりで、形も多様。
人間の目をひきつけ、感性を刺激するこの姿には、色彩感覚・対称性・季節感といった視覚的要素が詰まっています。
自然の美しさに着目し、それを観察・表現・デザインに活かす視点は、芸術教育の本質でもあります。
📐 数学(Mathematics)|配置・面積・対称性の最適化
「アジサイはどこまで目立てば、虫に見つけられるのか?」──
これは、面積・配置・形の最適化の問題です。
花の配置には放射状対称性やフィボナッチ数列など、自然界に見られる数学的な構造が関係していることも多く、「目立ちやすさ」と「壊れにくさ」のバランスは、図形と強度の関係として数理的に捉えることができます。
※各項目に添えた絵文字(🔬🛠🏗🎨✍️📐)は、塾長・古賀の工夫によるもので、公式のものではありません。
🧠 ガリレオ理数進学塾では、こうした「なぜ?」から始まる探究の視点を重視し、
中学受験や都立中高一貫校・都立高校入試につながる理科力を育てています。
🪻 前回の記事はこちら:
主役じゃないのに、なぜこんなに目立つ?アジサイに学ぶ“進化の戦略
▶ 中学受験コースの詳細はこちら
▶ 中学生コース案内はこちら
▶ 都立南多摩・武蔵など中高一貫校の数学・理科対策はこちら
▶ 無料体験・お問い合わせはこちら
- 投稿タグ
- STEAM教育, 中学受験生, 中学生, 探究的学習(IBL), 理科