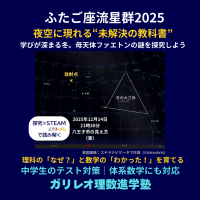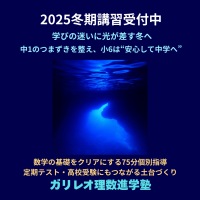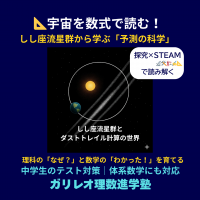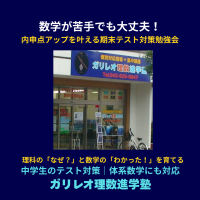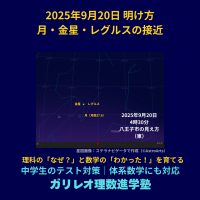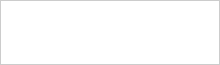中学生・高校生の多くが、いまや「当たり前」のように行っている“ながら勉強”。
音楽を流しながら、スマホ通知を見ながら…という学習スタイルは、一見リラックスできるように見えるかもしれません。
ですが、こうした習慣が「集中できない」「勉強しているのに成績が伸びない」といった悩みにつながっている可能性があるとしたら──?
本記事では、「ながら勉強」が学習効率に与える影響を、教育心理学・認知負荷理論の視点から解説し、成績アップにつながる集中力の高め方についても具体例を交えてご紹介します。

スマホを見ながら勉強していませんか?──“ながら勉強”は集中力を削ぎ、学習効率を下げてしまいます。
“ながら勉強”が集中力を削ぎ、学習効率を下げる理由とは?
心理学の研究では、人間の脳は複数の作業を同時に処理する「マルチタスク」が非常に苦手であることが知られています。
たとえば、YouTubeを流しながら勉強をしたり、LINEの通知が入るたびにスマホを手に取ってしまうような状況では、脳はタスクの切り替えにエネルギーを消耗し、本来の学習内容に集中できません。
このように「注意が分散した状態」は、認知心理学でいうところの「高い認知負荷」を生み出し、ミスや記憶定着の低下につながるのです。
実際に起きている「ながら勉強」の影響とは?
情報量が多すぎたり、考えることが多いときには、脳が一時的に混乱してしまいます。
これは、処理すべき情報が一度に多すぎると、パフォーマンスが低下するという、心理学の「認知負荷理論(Cognitive Load Theory)」にもとづいた現象です。
たとえば、負の数・文字の扱い・関数のグラフの読み取り・平方根など、新しい単元、特に抽象的な概念や記号を扱うとき、
それまでなら間違えなかったはずの基本的な計算で、急にミスが増えることがあります。
これは脳が情報過多になり、基本操作にまでリソースが回らなくなっていることの表れです。
そして、そこに“ながら勉強”のような外的刺激が加わると、この認知負荷の影響がさらに顕著に表れます。
特に、数学や理科のように「読み取り・思考・計算」をすべて必要とする教科では、その影響は無視できません。
● 文章題で情報の読み落としがあり、式が立てられない
● 連立方程式の解で x = 3 までは出せたのに、y を求め忘れてしまう
こうしたミスは、ふだんなら考えられないような“思考の抜け落ち”であり、
脳の処理能力が一時的に低下しているサインとも言えます。
【科学的根拠】マルチタスクは脳に負担をかける
🎧「音楽がないと集中できない」は本当?
「静かだと落ち着かない」という生徒もいますが、
それは“音楽で集中している”のではなく、
「音楽で気を紛らわせている(=気が散っている)」状態です。
特に、歌詞つきの音楽や、リズムが強調された楽曲は、
無意識に脳が意味処理を始めてしまい、思考系の学習(数学や理科)には不向きです。
📵また、「LINEの通知が入るだけで、英語の暗記内容が定着しづらくなる」ことも知られています。
これは「記憶の干渉」と呼ばれる現象で、新しい刺激が先に学んだ情報を邪魔してしまうからです。
✅ このように、“ながら勉強”によって集中力や記憶力が削がれてしまうことは、多くの心理学実験で実証されています。
参考文献:
-
Ophir et al. (2009). Cognitive control in media multitaskers.
-
Ward et al. (2017). Brain drain: The mere presence of one’s own smartphone reduces available cognitive capacity.
-
Salamé & Baddeley (1989). Effects of background music on phonological short-term memory.
集中力を高めるために、家庭でできる工夫
📱 スマホは別室に置く
通知音が聞こえるだけで集中力は下がります。完全に視界から外すのが理想です。
🎧 音楽は“環境音”まで
無音がつらい場合は、クラシックや自然音など“言語を含まない音”にしましょう。
⏱ ポモドーロ法を活用する
25分集中+5分休憩のサイクルで、集中とリラックスのリズムをつくる方法です。
🪑 学習前に机を整える
視界に余計なものがないだけで、脳の負荷が軽減され、集中しやすくなります。
🗣「今日は何をやるの?」と声をかける
目標を口に出すだけで、集中の質が大きく変わります。
ガリレオ塾での集中力を高める工夫
ガリレオ理数進学塾では、「ただ静かなだけの空間」ではなく、“集中が持続する学習空間”をつくることを大切にしています。
そのため、以下のような細かな工夫を日々の授業で実践しています。
🎶 クラシック音楽で“静かすぎない集中空間”を
完全な無音はかえって緊張や不安を引き起こすこともあります。
当塾では、穏やかなクラシック音楽を環境音として活用し、集中を妨げずに安心感を与える空間を整えています。
👀 一人ひとりの「集中の波」を見極めた声かけ
集中が高まっているときにはあえて静観し、
集中が切れかけた瞬間に「ちょっと図を描いてみようか」などと自然に促すようにしています。
タイミングを外すと逆効果になるため、塾長が常に生徒の表情や手元を観察しながら対応しています。
✍️ “手を動かしながら考える”習慣を徹底
「解き方が分からない」と手を止めてしまったときには、
「問題の番号だけでも書いてごらん」「途中式だけでも書いてみよう」と声をかけます。
このように行動を先に起こすことで、思考が再起動されることは多くの研究でも指摘されており、実際に多くの生徒がこの一歩から集中を取り戻しています。
🌱 小さな達成を見つけて認める指導
例えば、「この1行までは合ってるよ」と部分的な達成に注目して声をかけることで、
生徒自身が「できる部分」を再認識し、自信と集中力を回復することがあります。
ガリレオ塾では、「できたか・できなかったか」だけでなく、「どこまでできたか」にも目を向けた声かけを大切にしています。
🔁 類題での“再挑戦”で集中のリズムをつかむ
解説を聞いて「分かったつもり」になっても、定着しているとは限りません。
そこで、類題にすぐ取り組んでもらい、「あれ、また忘れてる…」という小さなズレをその場で修正します。
“できた実感”が積み重なることで、集中力は自然と持続していきます。
こうした一つ一つの工夫が、生徒一人ひとりの「集中できる力」を育むベースとなっているのです。
まとめ:「ながら勉強」こそ、成績停滞の元凶!
“ながら勉強”は、集中力を削ぎ、脳に無意識の負荷をかける行為です。
気づかないうちに「やってるのに成績が上がらない」状態を生み出してしまいます。
小さな習慣の見直しが、大きな成果の第一歩です。
ぜひ、ご家庭でも“集中できる環境”の工夫を取り入れてみてください。
📘 ご相談・お問い合わせはこちら:
▶ ご相談・お問い合わせ・無料体験はこちら
▶ 中学生コース案内はこちら
▶ 都立南多摩・武蔵など中高一貫校の数学・理科対策はこちら
対象中学校:椚田中・横山中・陵南中・浅川中・館中・七国中・南多摩中等教育・穎明館・工学院 など
対応学年:中1〜中3/中高一貫校生/中学受験生/小4~小6/(高校生は現在定員のため募集停止)