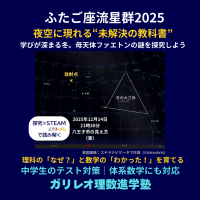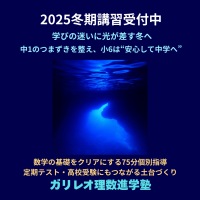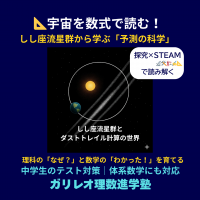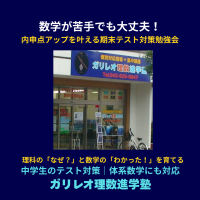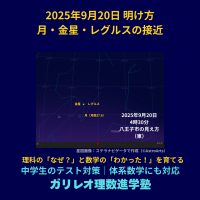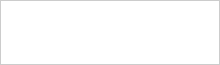※本記事は【2016年】当時の都立高校入試問題をもとに構成されています。
教育現場における出題の質や検証のあり方について記録したものです。
未来の受験生にとって、公平で正確な試験が実施されるよう、今後も注視してまいります。
問題の背景──金星の「見かけの位置」を問う設問
平成28年度の東京都立高校入試・理科の大問3(問1)では、
「日の出前の東の空に見える金星の位置」を選ばせる問題が出題されました。
「8月14日の数日後から,日の出の前の東の空に金星が観察できるようになった」
この記述は、太陽・金星・地球が一直線(会合)に並んだタイミングが8月14日頃であったことを示しています。
設問の日時は「3月24日」──143日前の配置を考える
問1の設定日は3月24日です。
したがって、会合日(8月14日)から143日前の天体配置を想定する必要があります。
このとき、金星と地球の公転の進み具合の差を考えることで、位置関係を導くことができます。
公転速度の差から「角度差」を計算してみる
問題文で与えられている情報は以下の通りです。
- 金星は 0.62年で公転(=226日程度)
- 地球は 1年で公転(=365日)
これらから、1日あたりの公転角度を計算すると:
- 金星:360 ÷ 226 ≒ 1.59度/日
- 地球:360 ÷ 365 ≒ 0.99度/日
- 差:1.59 − 0.99 = 0.60度/日
したがって、143日前には:
0.60 × 143 ≒ 85.8度
つまり、地球と金星のなす角が約85.8度開いた位置関係にあるとわかります。
図3の選択肢の中でこれに最も近いのが、「ウ」の位置です。
中学理科では扱わない知識──では正答は?
ここで考えておきたい点として、このような角速度の差をもとにした角度計算は、
中学校の理科では正式に教わる内容ではありません。
ただし、発展学習として取り扱うことはあり、私国立高校の理科入試では頻出のテーマでもあります。
また、中学受験の理科では一般的に出題されており、中学数学の知識と組み合わせれば、自力で導き出せる生徒も少なくなかったと思われます。
東京都教育委員会の見解と問題点
ところが、東京都教育委員会は、模範解答として「イ」で問題ないとしています。
その理由は、「このような計算は中学理科では扱わないため、図や見た目から判断させる問題だった」という立場です。
また都教委は、〔問1〕については<観察1>と<結果1>の情報のみをもとに解く設計であり、<結果2>に示された「金星の公転周期」や「8月14日の会合日」などは、あくまで問2以降のための追加情報であって、問1では使用を想定していなかったと説明しています。
たしかに、数学の入試などでは、問ごとに前提条件が異なり、それぞれの設問において与えられた情報だけで考えるのが一般的です。
しかし今回の問題は、実在の天体現象を扱い、「平成27年」「3月24日」「8月14日」といった具体的な日付が明示されています。
このような構成であれば、金星と地球の公転周期の違いから角度差を計算し、位置関係を推定する──つまり<結果2>を活用するという考え方は、むしろ科学的に自然で妥当なものです。
加えて、「<結果2>を使ってはいけない」といった明確な制限も設問文には記されておらず、資料として同じページに掲載されていた以上、生徒が参照し、そこから論理的に解を導くのは当然の思考過程と言えます。
したがって、より高い理科的理解や計算力をもとに「ウ」にたどり着いた生徒が、「出題意図に沿っていない」という理由だけで不正解とされる可能性があったことは、教育の観点から見てもきわめて残念であり、科学的思考を重視すべき入試における評価のあり方として、大きな課題を残すものです。
提言──正しく考えた生徒が損をしないために
問題の解き方に複数の理にかなった考え方が存在する場合、採点基準もその多様な思考を尊重する姿勢が求められます。
たとえば、公転周期と角速度の差に着目して「ウ」と論理的に導き出した生徒がいたとすれば、その考察力は評価されるべきです。
こうしたケースでは、模範解答だけにとらわれず、妥当な解法を認める柔軟な採点体制が不可欠です。
受験生の努力を正しく評価するためにも、検証可能で公平な設問づくりとともに、複数の正解や正当な根拠を許容する評価方針が今後の入試には求められます。
中学生・保護者の皆さまへ
今回のようなケースは、「理科の考え方」を深く学ぶ良い機会でもあります。
公転周期・角速度・論理的な検証による解答──こうした力は、入試だけでなく、社会に出ても必要とされる本物の力です。
ガリレオ理数進学塾では、そうした考える力・探究する力を、日々の学びの中で育てていきます。
※問題画像は著作権の都合上、当サイトでは掲載しておりません。問題文や図のご確認は、東京都教育委員会の公式資料をご参照ください。